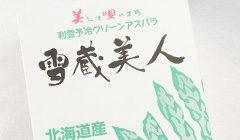|
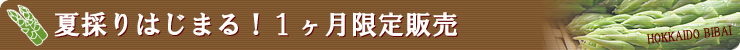 |
 |
東方には夕張山系の山並みが続き、 西方には石狩川が流れる町、美唄(びばい)。 この美唄で、とても貴重な夏採りアスパラを栽培しています。 「こもれび栽培」という名前の通り、直射日光を 当てすぎないようにしながらも養分を吸収し、 初夏のアスパラと同じように、 甘く柔らかいアスパラを作り出すのです。 「夏も美味しいアスパラを食べたい!」 のお声にお応えいたしました。 |
| この栽培方法は北海道ではとても貴重で、
青果市場でもとても価値の高い物になっています。 バーベキューの機会も多い、 真夏に、とっても美味しいアスパラを、 北釧水産では、今年も期間・数量限定で販売いたします! |
 |
美唄(びばい)の土壌は有機質をふんだんに含み、 泥炭土壌で育ったアスパラは糖度が高く、 ビタミンなどの養分がたっぷりです。 しかし美唄の農家さんは、もっと美味しいアスパラを 作るために研究に研究を重ね、低農薬・減農薬で作ったお米から出る、 有機質の籾(もみ)殻で作った堆肥を土壌に含ませて 窒素分が豊富な土作りを行っています。 籾殻くん炭は吸水性が良く、土壌の酸素供給を促し、 保水性を高め太陽熱の吸着・地熱の向上する作用があります。 |
 |
| 更に米作に適した石狩川の水と盆地特有の
寒暖差によって甘みが増し、太くてやわらかい、 根元まで食べる事ができるアスパラが採れるのです。 お客様からは「穂先はまるでとうもろこしの甘さですね!」と おっしゃっていただける程、感激の美味しさのグリーンアスパラが今年も育っています。 また、消費者との信頼関係を深める事を 目指す活動として、生産者が栽培履歴の記帳を行い、より安全で安心なアスパラ作りに励んでいます。 |
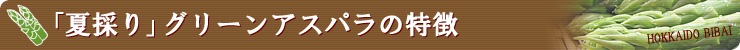 |
 |
通常の栽培方法のアスパラは穂先が紫色に比べて、 夏採り(立茎栽培)のアスパラは全体的に淡い緑色をしています。 春のものよりも柔らく、甘みがすっきりしているので 茹でる、焼くのはもちろん、薄くスライスして生でサラダにするのもお勧めです。 立茎栽培は最初少し収穫しただけで剪定しながら良い茎だけを残し その茎を伸ばしていきます。 |
| 伸びた茎は小さな竹林のようになり、その下の畑から出てくる若茎を収穫します。 竹林の部分が活発な光合成を行って若茎の成長を促し、結果的に収量を増やすことに成功しました。 この栽培方法は栽培の普及員がアスパラ林から差し込んでくる夏の日差しの美しさを表現して 「こもれび栽培」と名付け、以後美唄では立茎栽培のことを「こもれび栽培」とよんでいます。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
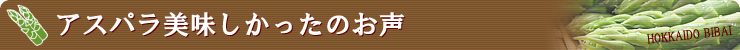 |
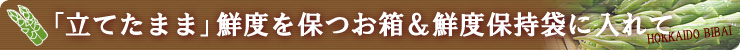 |
立ち野菜のグリーンアスパラは、寝かせると立ちあがろうとする さらに、採れたての美味しさを長く保つため この袋は一見完全に密封されているように見えますが、 酸素と二酸化炭素をバランスよく、無駄なエネルギーを使わない |
|
 |
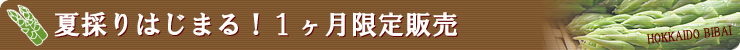 |
 |
東方には夕張山系の山並みが続き、 西方には石狩川が流れる町、美唄(びばい)。 この美唄で、とても貴重な夏採りアスパラを栽培しています。 「こもれび栽培」という名前の通り、直射日光を 当てすぎないようにしながらも養分を吸収し、 初夏のアスパラと同じように、 甘く柔らかいアスパラを作り出すのです。 「夏も美味しいアスパラを食べたい!」 のお声にお応えいたしました。 |
| この栽培方法は北海道ではとても貴重で、
青果市場でもとても価値の高い物になっています。 バーベキューの機会も多い、 真夏に、とっても美味しいアスパラを、 北釧水産では、今年も期間・数量限定で販売いたします! |
 |
美唄(びばい)の土壌は有機質をふんだんに含み、 泥炭土壌で育ったアスパラは糖度が高く、 ビタミンなどの養分がたっぷりです。 しかし美唄の農家さんは、もっと美味しいアスパラを 作るために研究に研究を重ね、低農薬・減農薬で作ったお米から出る、 有機質の籾(もみ)殻で作った堆肥を土壌に含ませて 窒素分が豊富な土作りを行っています。 籾殻くん炭は吸水性が良く、土壌の酸素供給を促し、 保水性を高め太陽熱の吸着・地熱の向上する作用があります。 |
 |
| 更に米作に適した石狩川の水と盆地特有の
寒暖差によって甘みが増し、太くてやわらかい、 根元まで食べる事ができるアスパラが採れるのです。 お客様からは「穂先はまるでとうもろこしの甘さですね!」と おっしゃっていただける程、感激の美味しさのグリーンアスパラが今年も育っています。 また、消費者との信頼関係を深める事を 目指す活動として、生産者が栽培履歴の記帳を行い、より安全で安心なアスパラ作りに励んでいます。 |
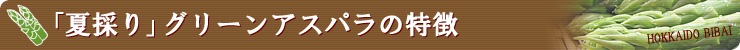 |
 |
通常の栽培方法のアスパラは穂先が紫色に比べて、 夏採り(立茎栽培)のアスパラは全体的に淡い緑色をしています。 春のものよりも柔らく、甘みがすっきりしているので 茹でる、焼くのはもちろん、薄くスライスして生でサラダにするのもお勧めです。 立茎栽培は最初少し収穫しただけで剪定しながら良い茎だけを残し その茎を伸ばしていきます。 |
| 伸びた茎は小さな竹林のようになり、その下の畑から出てくる若茎を収穫します。 竹林の部分が活発な光合成を行って若茎の成長を促し、結果的に収量を増やすことに成功しました。 この栽培方法は栽培の普及員がアスパラ林から差し込んでくる夏の日差しの美しさを表現して 「こもれび栽培」と名付け、以後美唄では立茎栽培のことを「こもれび栽培」とよんでいます。 |
| 栽培法 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 慣行栽培 | 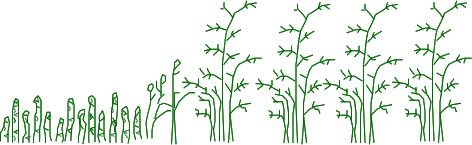 |
|||||
| ●春芽の収穫後は、茎を伸ばして次年度の養分を蓄える | ||||||
| こもれび栽培 (立茎栽培) |
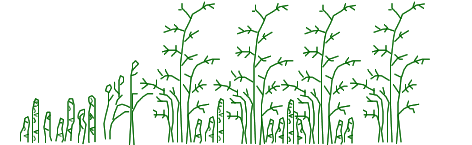 |
|||||
●春芽を収穫した後に、親茎を立てて夏芽を収穫する |
||||||
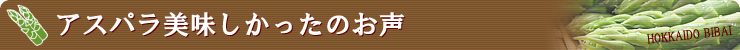 |
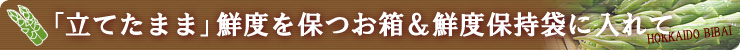 |
立ち野菜のグリーンアスパラは、寝かせると立ちあがろうとする さらに、採れたての美味しさを長く保つため この袋は一見完全に密封されているように見えますが、 酸素と二酸化炭素をバランスよく、無駄なエネルギーを使わない |
|